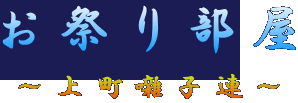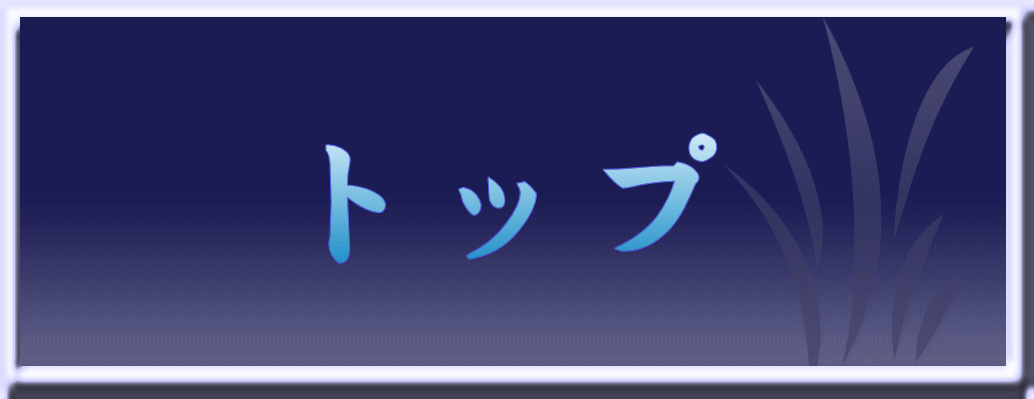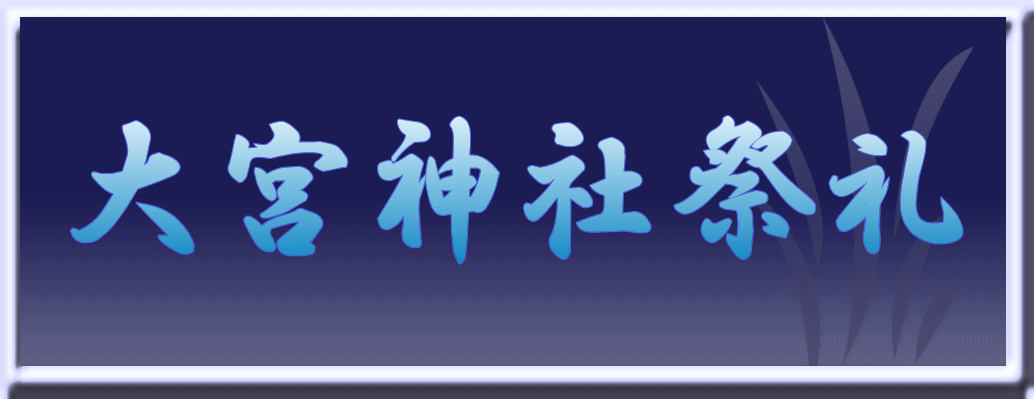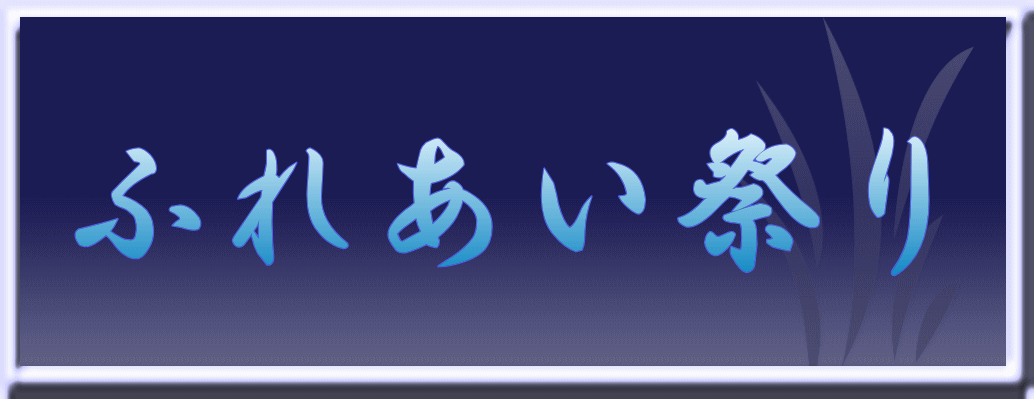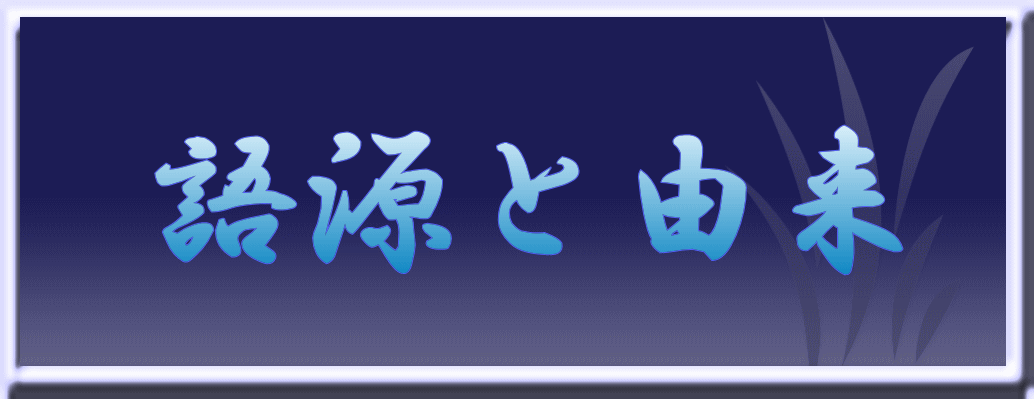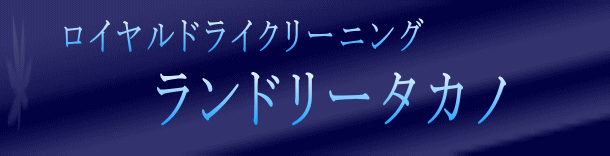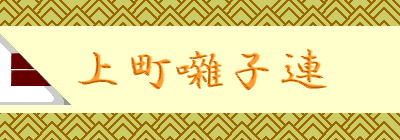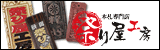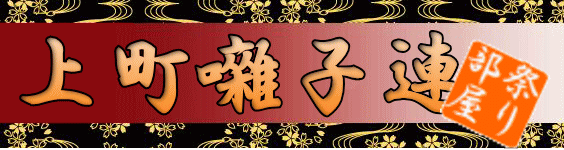5月4~5日の節句に行われ、子どもたちの健やかな成長と五穀豊穣を祈る。神輿・大鉾・猿田彦が旧玉造地内を練り歩き、霞ヶ浦浜地先でお浜降りをし町内のお仮屋に鎮座する。
祭りの最後を飾るのが流鏑馬である。現在は騎乗しないが、静寂な境内の的納めの神事となる。
祭囃子は祭に付随する音楽を総称したもので、各地域にあるそれぞれの祭に密着して発展してきたものである。日本全国で同じ曲や楽器構成を指すのではなく、一つの起源に遡ることができるものでもない。
関東の祭囃子は江戸時代の享保年間(1716~1736)に現在の東京都葛飾区金町(武州葛飾郡金町村)の香取大明神(現在の葛西神社)の神主、能勢(のせ)、環(たまき)が村内の若者を集めて敬神の和歌にあわせて拍子をつくり和歌囃子を教えたのが始まりと言われている。
関東の祭囃子は江戸時代の享保年間(1716~1736)に現在の東京都葛飾区金町(武州葛飾郡金町村)の香取大明神(現在の葛西神社)の神主、能勢(のせ)、環(たまき)が村内の若者を集めて敬神の和歌にあわせて拍子をつくり和歌囃子を教えたのが始まりと言われている。
そして、その囃子に獅子や滑稽面の踊りをあわせ、葛西囃子となり、やがて神田、目黒等に
広まったと言われています。
広まったと言われています。
語源は竈(かまど)の火を竹筒で吹いている「火男」がなまったものとされる。
家運や人の運勢はよく「火」にたとえられ、家運の隆盛を「火の勢い」・衰微は「火が消えたようだ」と言い、また「祖先の火を絶やすな」という言葉はこの火を絶やさず子孫へ伝え続けることを言います
火を絶やさず守る火男(ひょっとこ)は家運の隆盛と子孫の繁栄を意味し、縁起ものとしてお祝いの席には必ず登場するようなりました。
現在ではおかめと共に招福の象徴として扱われるようになり、「笑う門には福来る」という笑いを誘うため滑稽化されてきた。
頬が丸く張り出した形が瓶(かめ)に似ていることから名付けられたとされる。
また、おかめは健康で聡明な心のやさしい女性を意味しており、たくさんの福徳を持っているのでお多福(おたふく)とも呼ばれ、縁起が良いとされている。
稲作には、穀物を食するネズミや土手に穴を開け水を抜いてしまうハタネズミの被害があった。
きつねがネズミの天敵であった為、田の付近に祠を建て好物の油揚げ等で餌付けし、稲や穀物を守ったという。
このことから五穀豊穣・商売繁盛の象徴として扱われており、稲荷神の神使として信仰されている
日本で一番古い伝統芸能とされている。
獅子頭を頭にかぶって舞う伝統芸能 獅子舞は、日本各地の正月行事や晴れの日に舞われ、幸せを招くと共に厄病退治や悪魔払いとして古くより伝えられています。
獅子に頭をかまれると、その年は無病息災で元気で過ごせるという言い伝えがあり、。獅子舞は大自然の霊力を我々に授けてくれます。
頭に金色の角のようなもの(ギボシ)がある方がオスらしい。