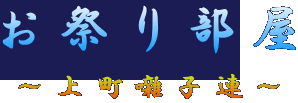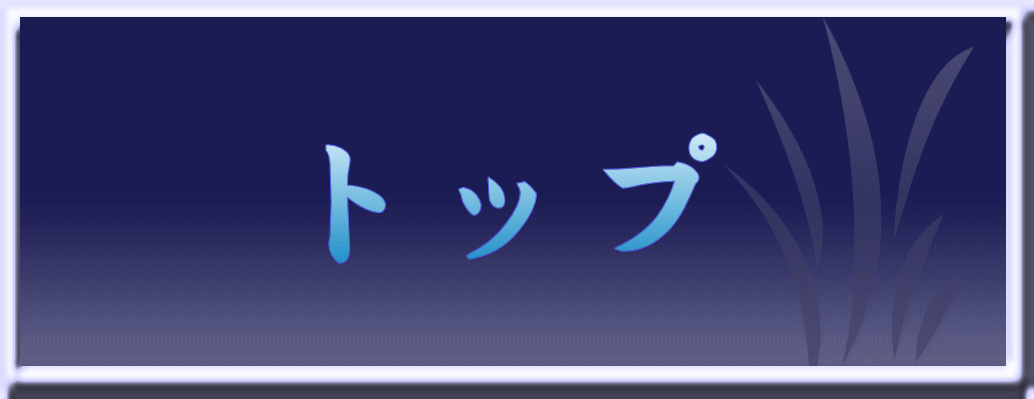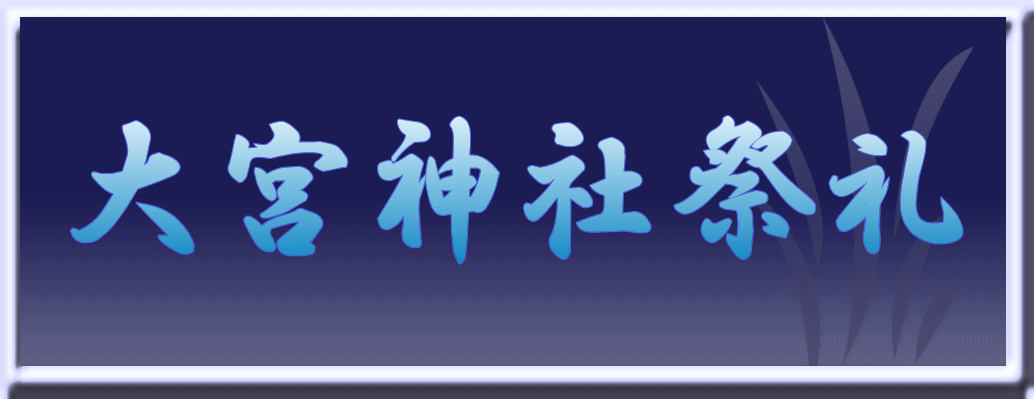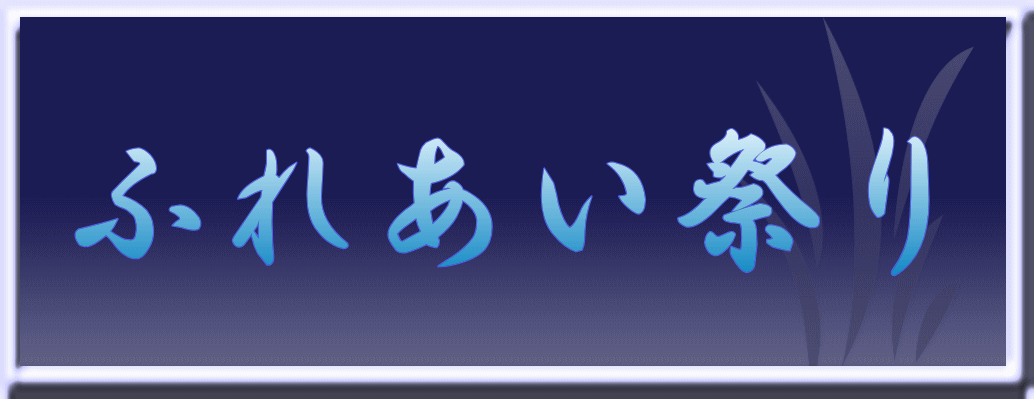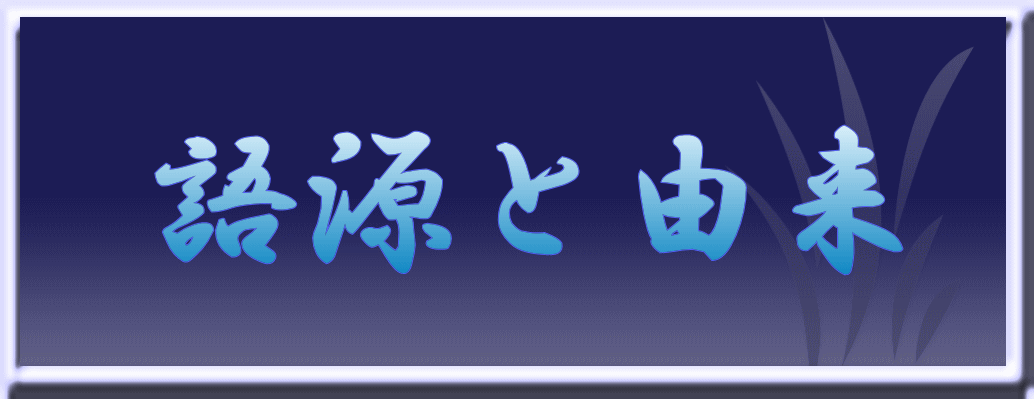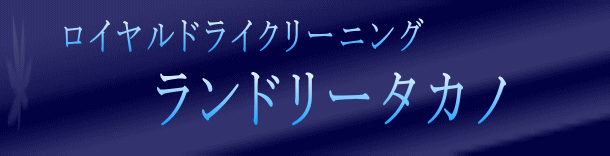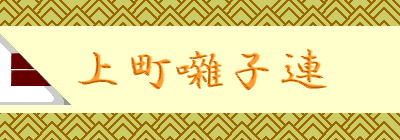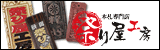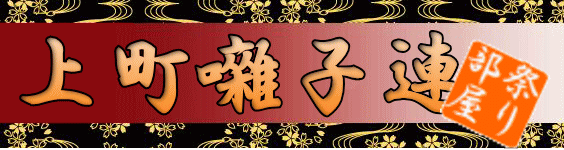初代玉造城主がはじめたと伝えられる祭礼
初代玉造城主がはじめたと伝えられる祭礼
5月4~5日の節句に行われ、子どもたちの健やかな成長と五穀豊穣を祈る。神輿・大鉾・猿田彦が旧玉造地内を練り歩き、霞ヶ浦浜地先でお浜降りをし町内のお仮屋に鎮座する。
祭りの最後を飾るのが流鏑馬である。現在は騎乗しないが、静寂な境内の的納めの神事とな
る。
4日は宵祭り、神輿が御仮屋へ渡御。5日は午前中に神輿が出て、お浜降りの後還御。山車は4日、5日
●玉造大宮神社

祭神:武甕槌命(タケミガヅチノミコト)
天津彦穂瓊々杵命(アマツヒコホニニギノミコト)
配祀:経津主命・倉稲魂命・菅原道真公・大山咋命
創建:和銅六年(伝)
境内の忠魂碑には天狗党の一員として慶喜に会えず越前敦賀で無念の死を遂げた人々の名が記されている。
●神輿
●大鉾(オオホコ・オオボク)
槍や薙刀の前身となった長柄武器(矛)が大型化し祭器として用いられるようになったもの
●鼻天狗(ハナテング)
日本神話に登場する神・神輿の先導を務める
●山車
上町(カミチョウ)

囃子は石岡染谷流 上町囃子連 山車人形は木花咲耶姫
本町(ホンチョウ)

囃子は石岡三村流 本町囃子連 山車人形は日本武尊
諸柄(モロカラ)

囃子は石岡三村流 諸柄囃子連 山車人形は聖徳太子
●幌獅子(ホロジシ)
●囃子
玉造のお囃子は石岡系囃子 大太鼓1、小太鼓2、笛1、鉦1の五人囃子が基本です。大太鼓は通称「おおど」、小太鼓は「つけ」、鉦は「ちゃり」と言われています。また鼓を使用する流派もあります。山車で演奏する場合は山車進行方向左側に太鼓を並べるのが特徴です。
曲目は、
・仁羽(ニンバ) ひょっとこ踊りに用いられる。
・四丁目(シチョウメ) おかめ踊りに用いられる。
・親馬鹿(シンバカ) シンバと呼ばれることが多い。きつねや獅子舞に用いられる。
・さんぎり 儀礼的な曲で、祭礼の最初と最後(山車出発時と帰着時)に演奏する。踊りは無い
動画蔵
写真館 2007年
→行方市商工会HPへ
![]() 大宮神社
大宮神社 ![]() 御仮屋
御仮屋 ![]() 上町 詰所
上町 詰所 ![]() 本町 詰所
本町 詰所 ![]() 諸丙 詰所
諸丙 詰所
![]() 駐車場
駐車場 ![]() 露店
露店
より大きな地図で 大宮神社例大祭 を表示