標準営業約款(Sマーク)とは
|
この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。 この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が営業を行いたい場合は、各都道府県の生活衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成16年3月現在、全国で約9万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。 また、標準営業約款では、法律に基づき業種ごとに次の3つの基本事項を定めており、この約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字「S」を取ったものです。 1. 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項(Standard)
2. 施設又は設備の表示の適正化に関する事項(Safety)(Sanitation)
3. 損害賠償の実施の確保に関する事項
このように標準営業約款制度は、あくまでも消費者利益擁護の観点から、消費者の選択の利便を図るという目的で創設されたもので、営業店にとっては、登録店に加盟することにより直ちに顧客が増加し、売上の増加につながるといったものではないところから、この標準営業約款への登録について営業者の理解を受けることは難しい面もありますが、標準営業約款制度の精神を十分理解した登録加盟店が増加し、技術・安全・衛生面等で業界全体のレベルアップが図られることにより、業界に対するさらに一層の消費者の安心と信頼が深まり、これが個々の営業店の経営の安定と活性化、繁栄につながるものと考えます。 |
|
(参 考) 標準営業約款制度創設の背景 生衛業サービスは、サービス内容の多角化、技術の高度化により、サービスの内容が一見しただけでは消費者に分かりにくくなっており、また、サービス内容も業者によりまちまちのため誤認を生ずることもあり、特に初めて利用するお店の場合消費者は若干の不安を覚えるものである。 この懸念を解消するためには、各営業店が自己のお店のサービス内容等を事前に消費者に明確に知らせることが必要であり、これを実行することによって消費者の不安を取り除き、安心して利用してもらうことができる。このようなこともあり、昭和48年、国民生活審議会から「環衛サービス業に係る消費者保護について」と題して、理容、美容、公衆浴場およびクリーニングのサービスに共通する対策の方向、具体的問題点と対策についての答申がなされた。 この答申の主な内容は消費者保護の観点から、これらの業種について、(1)衛生、安全の確保、(2)サービスの表示、(3)公正・自由な競争の促進、(4)損害賠償制度・苦情処理体制の整備等の施策を講じる必要があるというものであった。 標準営業約款制度は、この答申の精神を尊重して、利用者や消費者の選択の利便を図るため、昭和54年に「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」の改正により創設されたものである。 |
|
「環衛サービス業に係る消費者保護について」 国民生活審議会答申抜粋 ― 昭和48年2月27日 ― 環境衛生業種は、いずれも国民の生活に密着したサービスを提供しているが、理容、美容、公衆浴場およびクリーニングは、身体の清潔の保持等のためにきわめて重要なサービスである。 しかしながら、これらのサービスは、その性質上、生産性の向上が難しいこと等により料金が上昇しており、加えて、安全、衛生の確保、サービス内容の表示などの面においても十分とはいえない。公衆浴場においても近年廃業するものがあい次、入浴機会が失われつつあるなど、消費者の苦情を生ぜしめるところとなっている。 消費者の立場から、 1.提供されるサービスが衛生的かつ安全であること。 2.サービスの内容の多角化と同時にその表示が十分に行われ、消費者の選択性が確保されていること。 3.サービスが自由な競争を通じて提供されること。 4.消費者の被害、苦情が適切に救済されること。 との基本的認識のもとに、以下に述べる施策を講ずる必要がある。 (以下、略) |
厚生大臣認可クリーニング標準営業約款登録店
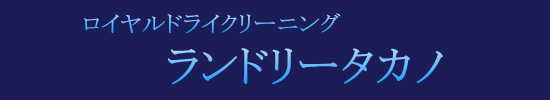
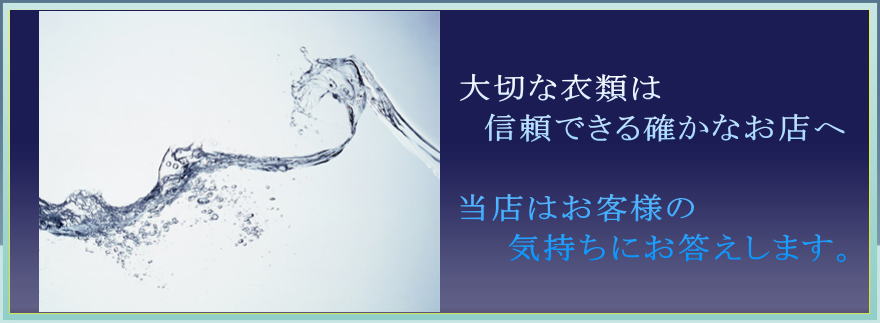
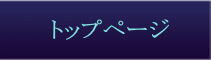
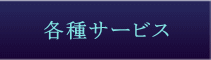
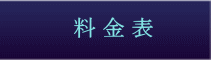
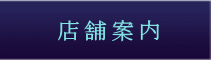
 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。
標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(以下、「生衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に生衛業の基本法である「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「生衛法」という。)を改正し、創設されたものです。